�]�[�ǂ̗\�h�Ɏg�������i��ÊW�Ҍ����j
- �]�[�ǂ̍Ĕ��\�h�Ɏg������
- �]�[�ǂ��N�����@���ɂ͂R�̃^�C�v������
- �]�[�ǂɂ͂������̃^�C�v������A���ꂼ��Ŋ댯���q���قȂ�A���̂��ߗ\�h�Ɏg�����܂��قȂ�@
- �������o����@���ɂ͓�̃^�C�v������A���ꂼ��̗\�h�Ɏg�����܂��قȂ�
- �R�ÌŖ�
- �V�����o���R�Ìō�
- �R������
- �A�X�s�����W�����}�[�A�X�s�����̎��K���p�ʂƂ�
- ��p�Ȃǂ���ۂ̃A�X�s�����̒��~���Ԃ̗���
- �p�i���W���i�`�N���s�W���j
- �N���s�h�O�����i�u���r�b�N�X�j
- �v���^�[���i�V���X�^�]�[���j
- �]�����w��̃K�C�h���C��
�]�[�ǂ̍Ĕ��\�h�Ɏg������
�]�[�ǂ̍Ĕ��\�h�Ɂu�R�����܁v���A�����ĐS�[�ד�����̔]�ǐ��̗\�h�ɂ́u�R�Ìō܁v���g�p�����B�R�����܂ƍR�Ìō܂̎g�������ɂ��ĉ������B
�]�[�ǂ��N�����@���ɂ͂R�̃^�C�v������
- ���𐫁ithrombotic�j�@�����d�����a�ςɂ�蓮���̋����X�ɐi�s���A�ŏI�I�Ɍ����ɂ��ǂ���^�C�v�B���ɓ����ǂ̕s����v���[�N�̔j�]�ɂ��}���ǂ��������ꍇ�����邪�A��ʂɏǏ��2�`3�������Ċɏ��i�s���ɑ������A���̊ԁA�Ǐ�̓��h�����������Ƃ������B�Ȃ��]�ꓮ���Ȃǂ̏ꍇ�ł͂P�T�Ԃ��炢�����đ����������J��Ԃ��Ȃ���Ǐ������邱�Ƃ�����B
- �ǐ𐫁iembolic�j�@�����߈ʕ� (�ǐ���)�ɏo�����������͂���A�ǐ��ƂȂ艓�ʕ��̔]�����ɗ���čs���ċ}���ǂ���^�C�v�B�Ǐ�͓˔��������B
- ���s�͊w���ihemodynamic�j�@�����̋߈ʕ��ɕǂ⍂�x�̋����邪�������s�Ȃǂ�ʂ��āA���i�͏ǏłȂ����x�̔]�������c���Ă�����(misery perfusion)������A�����ቺ�Ƃ���_�f���ǂ��������ۂɁA�ł������̓͂��ɂ��������̋������A�������[�ǂɊׂ�a�ԁB���̑O�ɓ����Ǐ��TIA�i��ߐ��]��������j���J��Ԃ����Ƃ������B
�]�[�ǂɂ͂������̃^�C�v������A���ꂼ��Ŋ댯���q���قȂ�A���̂��ߗ\�h�Ɏg�����܂��قȂ�
�]�[�ǂɂ͎��̂悤�ȃ^�C�v������B���̂������N�i�[�ǂ��ł������A�ŋߔN�z�̕��𒆐S�ɐS�[�ד��ɂ�������������A���̂����Ŕ]�ǐ����������Ă���B�]�[�ǂ͉Ăɑ����X�������邪�A�]�ǐ��͊����~�G�ɑ����X��������B
- �玿�}�[�ǁi�A�e���[�����𐫔]�[�ǁj
- ���ʎ}�[�ǁi���N�i�[�ǁj�@
- BAD�ibranch atheromatous disease �j�@
- �]�ǐ��i�S�����]�[�ǂȂǁj
- ���E��]�[�ǁiwater-shed infarction�j
- �����𗣁i�ō��]�ꓮ���̈�ɑ������A�����n�ɂ�����j
- ��N�҂̔]�[�ǁi�R���������R�̏nj�Q�A���ۋؐ��ٌ`���@Fibromuscular dysplasi�A���������a�Ȃǁj
1.�玿�}�[�ǂ̌����̓A�e���[�������d���A�����Ċ댯���q�͍������ǂⓜ�A�a
���̃^�C�v�̔]�[�ǂ͈�ʂɔ玿�}�ƌ����A�]�̓����̒��ł��������ǂɋN����A�������ǁi�����ُ�ǁA���R���X�e���[�����ǁj�ⓜ�A�a���瓮���d���i�A�e���[���d���j���N�����A����ɂ���ċN����^�C�v�̔]�[�ǂł���B�܂蓮���d�����a�ς̋���x�����X�ɐi�s���A�ŏI�I�Ɍ����ɂ��ǂ���a�Ԃł���B�����āA���̃^�C�v�ł͑������ǂ��l�܂邽�߁A�]�[�ǂ��N�����ƁA��ʂɍL���͈͂̔]�[�ǂ��N�����B�Ⴆ�Ύ���ǂ�����Δ玿�����̕ǂ��l���邪�A���N�i�[�ǂł͎���͋N����Ȃ��B�Ǐ�͊ɏ��������ŁA�i�s�A���h���邱�Ƃ������Ƃ����B�Ȃ��s����v���[�N�̔j�]�ɂ��}���ǂ��������ꍇ������B
2.���ʎ}�i���N�i�j�[�ǂ̊댯���q�͍�����
�ד����d���ɋN��������ʎ}�[�������̌��lj�|�q�A���m�\�V�X��鋷��A�����ĕǂł���A�댯���q�͍������B���̕a���w�I�ω��͔]�[�ǂ݂̂Ȃ炸�]�o���������N�����Ƃɂ��Ȃ�B���N�i�Ƃ͐��m�`�[�Y�̐ؒf�ʂɂ݂����C���Ɏ��Ă��邱�Ƃ��炫�����O�ł���B
3.BAD�ibranch atheromatous�@disease�j
�玿�}����̐��ʎ}�J�����ɐ��������A�e���[���d���a�ς��N���Ƃ���J�����̕ǂɂ��A���ʂƂ��Đ��ʎ}�̕ǂ������������̂ł���B���ʎ}�̈�̍[�ǂ��N�������A���ʎ}�[�ǂƈႢ�A�玿�}�[�ǂ��Ȃ킿�A�e���[�������ǂƓ����댯���q�i�����ُ�ǁA���R���X�e���[�����ǂⓜ�A�a�j�ł���B����BAD�͋}�����]�[�ǂ�10�`17���A��S�����]�[�ǂ�15���`25�����߂�BBAD�́A���ʎ}�ɉ������ג����]�[�ǂɂȂ邽�߁ACT��3�X���C�X�ȏ�A������]�[�ǂ��݂���BBAD��25�`39���ɏǏ�̐i�s���݂��邱�Ƃ���A���nj�A���邢�͓��@��ɏǏi�s���邱�Ƃ������A�^���@�\�̉��ǂ��Ȃ��Ƃ�������������B
4.�]�ǐ�
��\�I�Ȃ��̂��S�����]�ǐ��icardioembolic�j�B�ʏ�玿���܂�[�ǂ��A�Ǐ�͓˔��������B�ǐ����Ƃ��Ă͐S�[�ד��A�}���S�؍[�ǁA�g���^�S�؏ǁA�l�H�قȂǂ���b�����Ƃ��č��S���A���S�[�A���S���ɏo�����Ǎ����ɂ����́A�܂��͔S�t��A�n�ҁi�䂤�����F�������S�������ɂ��ې��̂��ԁj�Ȃǂɂ��B�nj�̍ĊJ�ʂɂ��o�����[�ǂ�F�߂邱�Ƃ������B����ȊO�� ���nj����ǐ�(artery to artery embolism)���Ȃ킿�����d���ɂ��z���������Ƀv���[�N�i����j������A��������͂��ꂽ���������ʂ̒���]�����܂Ŕ�сA������ǂ����ꍇ�ȂǁA���邢�͑哮�������]�ǐ��A���Ȃ킿��s�哮������|�������Ă̕����ɂ����銟��d������𗣂���̍ǐ��ǂ�����B���̂悤�ȏꍇ�A�V�����[�𗁂т��悤�Ȕ玿�}�̈�̏��[�ǂ̑����Ŕ��ǂ��邱�Ƃ������B
5.���s�͊w��
�Ⴆ�Γ����ǂ��邢�͒���]�����劲���̕ǂ̍ۂɁA����]�������ʕ������]������O��]��������̑������s�ɂ�茌�������낤���Ĉێ�����Ă���ꍇ�ȂǂŁA���������������ۂɓ����̟����ቺ���������Ĕ]�[�ǂɎ�����́B
�������o����@���ɂ͓�̃^�C�v������A���ꂼ��̗\�h�Ɏg�����܂��قȂ�
�����̗\�h�ɂ́A�����̓�����}����u�R������v�ƁA�Ìň��q�̓�����}����u�R�ÌŖ�v�Ƃ̂Q��ނƂ�����
�����ǂ̔����ɁA�����ł͌������A�Ö��ȂǂŌ��t���邽�߂ɋN���錌���ǂł͋Ìň��q�̓������d�v�ł���B���Ȃ킿�����������A�����̍��������ł͖��C�́i���艞�́j�傫���Ȃ�A����A�����̒x���A�����̒Ⴂ�Ö��ŏ������Ȃ�B�������ł���ۂɂ́A���́u���艞�́v�������e�����邪�A�u���艞�́v���傫���Ƃ���Ō������ł���ۂɂ́A�u�����v���ł��傫�ȓ������ʂ��B����A���艞�͂��������A�����̑ؗ����Ă���Ƃ���ł́A�t�B�u���m�[�Q�����͂��߂Ƃ���u�Ìň��q�v�̓����������ɂȂ邱�Ƃ��傫�Ȗ������ʂ��B�]���Ė��C�́i���艞�́j�̍��������ŁA�����d������̂ƂȂ錌���ǂ�h���ɂ́A�����̓�����}���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B����A���t���邱�Ƃ���̂ƂȂ錌���ǂȂǂł́A�Ìň��q�̓�����}���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B�����ŁA���S�ǁA�S�؍[�ǁA�]�[�ǂȂǁA�����ŋN���錌���ǂł́A��ɍR�����g���A�l�H�ْu���p��A�S�[�ד��A�[���Ö������ǁA�x�[�ǂȂǎ�Ɍ����̗����T�ɂ�錌���ǂł́A�R�ÌŖ�Ɏg���邱�ƂɂȂ�B
�Ȃ��A�����ƋÌň��q�Ƃ́A���݂��ɉe����������������邱�Ƃ�����A���҂̓����m�ɕ����邱�Ƃ�����ȏꍇ�������āA�R������ƍR�ÌŖ�Ƃ̗��҂��K�v�ɂȂ邱�Ƃ�����B
�R�ÌŖ�
�t�B�u������������ɂ́A�܂����Ǔ��炪�����đg�D���q�������Ɍ���A�Ìő�V���q�ƌ������������n�܂�B���Ƀv���g�����r���i�Ìő�Q���q�j���g�����r���ɕω����A�ŏI�I�Ƀt�B�u���m�[�Q�����t�B�u�����ɕς���B���̔����̍ۂɌ����Ìő�Q�A��V���q�i���ɑ�X�A��10���q�j�́u�r�^�~���j�ˑ����Ìň��q�v�ƌĂ�A����炪�̑��ō����ۂɃr�^�~���j��K�v�Ƃ���B���Ȃ킿�R�ÌŖ�Ƃ��Ă悭�g����u���[�t�@�����v�́A���̍�p�@������A�r�^�~��K�h�R��ƌĂ��B�܂�v���g�����r���Ȃnj��t�Ìň��q�̍����Ɍ������Ȃ��r�^�~���j�̓�����j�Q���邱�Ƃɂ��B���̌��ʂƂ��āA�ÌŌn�̓������}������A�R�������ʂ�����B���̍�p�ʂ���R�ÌŖ�������͍R�Ì���A�܂��͌��t�Ìőj�~��ȂǂƌĂ��B
�R�ÌŖ�̂������˖�Ƃ��Ă̓w�p�����A�ᕪ�q�w�p�����A�A���K�g���o���A�_�i�p���C�h�i�g���E���A�t�H���_�p���k�N�X���g�p����Ă���B�o�����^�ł���R�ÌŖ�ɂ́u���[�t�@�����v���g���Ă����B���[�t�@�����́A���ځA�Ìň��q��}����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���ݎn�߂����p�����肷��܂łɎ��Ԃ�������B�܂��A���̍�p�ɉe�������`�q���l�ɂ���ĈقȂ邽�߁A�������ɈႢ������A����ɑ̒���H�����e�Ȃǂɂ���Ă����ʂ��ς�邱�Ƃ�����B�����ŕ��p���́A���ʂ̒��x�����I�Ɍ������A���p�ʂ߂���K�v������B���̂��߁u�v���g�����r�����ԁiPT�j�����v���s���A��������ەW�����v���g�����r����iINR�j�ŕ\������B
���{�z��w��̃K�C�h���C���ɂ�郏�[�t�@�������^�ɂ�����PT-INR�̖ڕW�l�ł́A70�Ζ����ł�2.0�`3.0�A70�Έȏ�ł�1.6�`2.6��ڕW�Ƃ���Ă���B
��ٖ��ǐ��S�[�ד��iNVAF)�̃��[�t�@�����ɂ�錌���ǐ��ǂ̌��ʂ������������Ă̌����ɂ��ƁA���[�t�@�����𓊗^���Ă��Ȃ��ꍇ�̌����ǐ��ǂ̔��Ǘ��͔N����4.5%�ł������̂ɑ��āA���[�t�@�����𓊗^�����ꍇ�ɂ͔N����1.4%�Ɩ�70%���\�h�ł����Ƃ̂��Ƃł���B���[�t�@�����𓊗^����Ɣ牺���o���Ȃǂ̕p�x�͑����݂�ꂽ���A�]�o������@�A�A���A��p��v����悤�ȑ�o���̕p�x�ɂ͍��݂͂��Ȃ������Ƃ̂��Ƃł���B70�Έȏ�ł́APT-INR2.2����Əd�Ăȏo���������ǂ��݂��n�߁A2.6����Ƌ}���ɑ�������̂Œ��ӂ��K�v�ƂȂ�B
���[�t�@�����̌��ʂ̓r�^�~��K�ɂ���Č��シ��B�[���A�N�������̓��[�t�@�����̌��ʂ���߂�̂ŐH�ׂȂ��悤�Ɏw������K�v������B���[�t�@�����̍�p�������Ƃ��ẮA�R�Ă�܁A��M���ɏ����܁A���_�_�o�p�܁A�s�����p�܁A���A�܁A�������Ǘp�܁A��������ᇍ܁A�z�������܁A�ɕ����Í܁A�y�f���܁A���A�a�p�܁A�R���@�����Ȃǂ�����A����A��p����߂��Ƃ��đ�\�I�ȕ��̓r�^�~���j�ܗL�܂Ƃ��āA���e頏ǂ̎��Ö�O���P�[������B
�V�����o���R�Ìō�
���ă��[�t�@�����͒���I�Ȍ������K�v�Ȃ��Ƃɉ����A�H���Ȃǂ̉e�����₷���A��ɒ��ӂ��������Ȃ��B���̂��߁A����I�Ɍ������Ȃ��Ă��A���̗ʂ��g�����Ƃ��ł���o���ÌŖ�̊J�����i�߂�ꂽ�B2011�N1��21���A���ڃg�����r���j�Q����_�r�K�g�����G�e�L�V���[�g���^���X���z���_���i���i���v���U�L�T�J�v�Z��75mg�A���J�v�Z��110mg�j���������F���擾�����B�K���́u��ٖ��ǐ��S�[�ד����҂ɂ����鋕�����]�����y�ёS�g���ǐ��ǂ̔��Ǘ\�h�v�ł���A1��2��A1��150mg�̓��^����{�Ƃ��A�K�v�ɉ�����1��ʂ�110mg�Ɍ��ʂ���B�_�r�K�g�����́A�g�����r���������ʂɋ����I���t�I�Ɍ������邱�ƂŁA�g�����r���̐G�}������j�Q���钼�ڃg�����r���j�Q��p��L����B���Ȃ킿�g�����r���̊�����j�Q���邱�ƂōR�Ìō�p������B�_�r�K�g�����̑�ӂɂ�Cytochrome p-450 �͊֗^���Ȃ��̂ŁA�H���A���ݍ�p�Agenetic polymorphism �̉e�����ɂ����B
���[�t�@������ΏƂƂ��čs��ꂽ��3�����ۋ��������ł́A�_�r�K�g�����̗Տ��L�p����������Ă���B�S�[�ד����҂ŁA�]�����A�S�g�ǐ��ǂ��v���C�}���[�A�E�g�J���Ƃ����X�^�f�B�ł́A�_�r�K�g����110mg�P���Q�^�̓��[�t�@�����Ɨ�邱�Ƃ��Ȃ��A150mg�A�P���Q�^�̓��[�t�@�������L���ł������B�d�Ăȏo���������ǂ̓_�r�K�g����110mg�A�P���Q�^�Ŏ�����A150�r�A�P���Q�^�ł͗L�Ӎ��͂Ȃ������B�����Ĕ]�o���̓_�r�K�g�����ł̓��[�t�@�����̂P/3�ł������B�܂����{�l���܂ޑ�3�����ۋ��������ł́A21.4���ɕ���p���F�߂��Ă���̂ŁA�\���Ȓ��ӂ��K�v�ł���B��ȕ���p�́A�����s�ǁi3.0���j�A�����E�㕔�����ɁE�@�o���E���S�i�e1.1���j�Ȃǂł���A�d��ȕ���p�Ƃ��ẮA�o���i���W���o���A�����Ǐo���j������Ă���B�Տ���R�������ł́A�d��ȏo���͒�p�ʌQ��2.71��/�N�A���p�ʌQ��3.11��/�N�Ń����t�@������3.36�������������������B�܂����O���ꂽ���W���o���̔��Ǘ��������t�@����������錋�ʂƂȂ����B
��Ɍ����J���Ȃ���v���U�L�T�̎g�p�Ɋւ�����S�����o�Ă���A���̓��e�́A�v���t�Ìőj�~�܁u�v���U�L�T�J�v�Z���v�ɂ��āA�����Ǐo�����̏o��������p�ɂ�鎀�S�Ⴊ����Ă���A�X�ɒ��ӊ��N��O�ꂷ�邽�߁A�����̔��Ǝ҂ɑ��āA�u�g�p��̒��Ӂv�̉������s���ƂƂ��ɁA���W�҂ɑ��đ��₩�ɏ�����悤�w�������̂ł��`�����܂��B�v�܂����{�z��w���u�S�[�ד��ɂ�����R����Ö@�Ɋւ���ً}�X�e�[�g�����g2011/8/15�v�����\����Ă���B�ȏ���o�����X�N�ւ̒��ӁA�t�@�\�̊m�F�A����I�Ȑt�@�\�����Ȃǂ�K���s���K�v������B
�R������
�����̕\�ʂɂ́A���t���⌌�ǂɑ��݂���t�B�u���m�[�Q���A�t�H���E�E�B���u�����h���q�A�R���[�Q���Ȃǂƌ��������e�̂ƌĂ�镪�q�����݂��A����Ɣ����������Ďh�����A���ʂƂ��Č����̓����┽���������ɂȂ�B���̌��ʁA��������A����Ɍ����̓����������ɂ��镨�������o��������A�u�U���v�ƌĂ�鑫���o���A�~�Ղ̂悤�Ȍ`�ɕς���āA���ǂ̏����������ɂ������A���݂����������A����������Ă䂭�B
�����̓���������������̂�}���A�������ł��ɂ�������̂��R������ŁA���̂�����\�I�Ȃ��̂��A�X�s�����ł���B
�o���R������ɂ̓A�X�s�����A�N���s�h�O�����A�`�N���s�W���A�V���X�^�]�[���Ȃǂ�����B����ȊO�Ɍ��ʂ͎ア�ł����A�Z���N���[����P�^�X���R�������ʂ�����܂ł���B�A�X�s�����́A�����̓��������������邽�߂ɕK�v�ȃg�����{�L�T��A2�����V�N���I�L�V�Q�i�[�[�Ƃ����y�f�̓�����}���邱�Ƃɂ���āA�������m�̌����A�����̓����������ɂ��镨���̕��o��}�����ʂ�����B������A1���ōō��ɒB��2���ň��肷��i4���ԂōR������p�o���A10���ԖڂŌ��ʍō��ɂƂ�������������j�B�A�X�s�����̔]�[�Ǘ\�h���ʂ�15�����X�N�ጸ�Ƃ̕�A�]������TIA�ɂ����錌�ǃC�x���g�̔�����22���ጸ������Ƃ̕�����iATT�̕j�B
�A�X�s�����W�����}�@�\�A�X�s�����̎��K���p�ʂƂ́\
�A�X�s������1��75�`150mg�ōł��傫�Ȍ��ʂ�����Ƃ���Ă���B�����ÏW�������N����ƁA�����ɂ���A���L�h���_�́B�y�f�̓����ło�f�h2�i�v���X�^�T�C�N�����j�ƃg�����{�L�T�������o���B�v���X�^�T�C�N�����͌��ǂ̓���זE�ɂ���A�����̋ÏW��W���铭��������B�g�����{�L�T���͌��ǂ����k�����A�������ÏW�����铭��������B�A�X�s�����͂��̗��҂̓�����W�����p������A�g�����{�L�T���̓�����W�����ǂ��L�������̋ÏW��W�������A�v���X�^�T�C�N�����̓�����W�������̋ÏW�i������B���̌��ۂ��A�X�s�����W�����}�ƌĂԁB
�A�X�s���������ʂł���A�g�����{�L�T���̓����͗}���邪�A�v���X�^�T�C�N�����̓����ɂ͉e����^���Ȃ��B�܂�A80mg���x�̕��p�ł́A�g�����{�L�T���͂قڃ[���ɂȂ��Ă��܂����A�v���X�^�T�C�N�����͂܂�60�`80���c���Ă���B�����ŁA�]�[�ǂ̍Ĕ��\�h�ɂ́A80mg���x�̏��ʂ��p������B
��p�Ȃǂ���ۂ̃A�X�s�����̒��~���Ԃ̗���
�����̎����͖�10���Ԃł���A�A�X�s�����s�t�I�Ɍ�����}������̂ŁA�A���s�����ɖ\�I���������́A���̎����ł���10���Ԃ̊ԁA�@�\����~�����܂܂ƂȂ�B�܂茌���ɑ����p�͌����̎������Ȃ��Ȃ�Ȃ��Ə����Ȃ��B�����ŁA����𒆎~���āA���̌��ʂ����S�ɐ��̂�7�`10����ƂȂ�B
�p�i���W���i�`�N���s�W���j
������G�`�������^ADP��e�̂̑j�Q�ɂ��AGPIIb/IIIa�ւ̃t�B�u���m�[�Q���ւ̌�����}������B������C�����Z�x�̃s�[�N��2���Ԍ�ł��邪�A�����ÏW�}����p�͓��^��24���Ԃōő�ɒB����B�i�����Z�x�̃s�[�N�ƌ��ʂƂ̊Ԃɂ��ꂪ����j�B��p�̓A�X�s�����Ɠ������A�����̎����ƂƂ��ɏ�������B��ʂɓ�����2�`3���Ō��ʂ����A4�`7���ň��肷��B����p�̃`�G�b�N�̂��߁A�����2�T�Ԃ��ƂɌ��t�������s���K�v������B
�i�g�p���������̌x���F���𐫌��������������a�A���������ǁA�d�ĂȊ̋@�\��Q�Ȃǂ̏d��ȕ���p����ɓ��^�J�n��2�����ȓ��ɔ������A���S�Ɏ���������Ă���B�j
�N���s�h�O�����i�u���r�b�N�X�j
2006�N1��23���A�R������́u���_�N���s�h�O�����v�i���i���F�v���r�b�N�X���A�ʐ^�j�����F���ꂽ�B�N���s�h�O�����͉��_�`�N���s�W���i�p�i���W���j�Ɠ����A�`�G�m�s���W�����i��L����R������ł���B�̑��ő�ӂ��Đ�������銈����ӕ����A������̃A�f�m�V�����_�iADP�j��e�̂ɕs�t�I�Ɍ������邱�Ƃɂ��A�����I�Ȍ����ÏW�}����p������B��p�������Ԃ͖�10���ԁi�������̎��������j�Ńp�i���W���Ɠ����ƍl���Ă悢�B�N���s�h�O�����̍ő�̓����́u���S���v�ł���B�`�N���s�W���͍�p���������ʁA���𐫌��������������a�iTTP�j�A���������ǁA�d�ĂȊ̏�Q�Ȃǂ̏d��ȕ���p���m���Ă���A����畛��p�ɂ�鎀�S�������Ă���B������A�����J���Ȃ� 1999�N��2002�N�Ɍv2��A�ً}���S�����Ōx�����A�u���ÊJ�n��2�J���Ԃ́A2�T�Ԃ��Ƃɔ������Z��Ɗ̋@�\�������s���A�����Ƃ���1��2�T�ԕ��܂ł̓��^�Ƃ���v�Ƃ�����������݂��Ă���B
�v���r�b�N�X�̓A�X�s�����Ɣ�r����ƁA��2�N�ŐS���ǃC�x���g�i�]�[�ǁA�S�؍[�ǁA���ǎ��j���v���r�b�N�X�F5.32%�A����A�A�X�s�����F5.83%�ő����X�N����8.7%�ł������B���Ȃ킿�N���s�h�O�����̓A�X�s������8.7������L�ӂ̋������]�����ጸ���ʂ��������B���S���ɂ��Ă��N���s�h�O�����̓A�X�s������L�ӂɏ����Ă����B
�R����Ö@�g���C�A���@CAPRIE�����i1996�j
�N���s�h�O�����Q�̋������]�����A�S�؍[�ǂ܂��͌��ǎ��̔����̑����X�N�ቺ����7.3���ip��0.26�j�A�]���������̑����X�N�ቺ����8���ip��0.28�j�ł������B
�]�����K�C�h���C��2009
�nj����d���������i�������]�������邢�͐S�؍[�ǁj�̊�����L����B�n�C���X�N��ɂ����鋕�����]�����A�S�؍[�ǂ܂��͌��ǎ��̔������i3�N�ԁj�́A�N���s�h�O�����Q20.4���A�A�X�s�����Q23.8���B�N���s�h�O�����Q�̑����X�N�ቺ����14.9���ł������i95��CI 0.2�`7.0���j�ip��0.045�j�iNNT��3�N�̊ώ@��29�B�A�����̌����̑Ώۂɂ͓��{�l�͊܂܂�Ă��Ȃ��B
�N���s�h�O�����ƃA�X�s�����Ƃ̔�r�����ł́A�N���s�h�O�����̕���Q�̕����A�S���njn�̕a�C�̔��Ǘ���9���قǏ��Ȃ������B�`�N���s�W���i�p�i���W���j��ΏƂƂ�����d�ӌ���r�����ł́A�S���njn�̕a�C�̔��Ǘ\�h���ʂɍ��͂Ȃ��������A�d������p�̔��������`�N���s�W����菭�Ȃ������B
�`�N���s�W���ƁA�N���s�h�O�����̓A�X�s�����Ɣ�ׂČ��ǃC�x���g�ጸ���ʂ͂��ꂼ��10���A12�������Ă������A�L�ӂȍ��Ƃ͂Ȃ�Ȃ������iATT�̕j�B
EVEREST(Effective Vasccular Event Reduction after Stroke)
�R������p���Ă���3452��ɂ���2007�`2008�N�ɂ����čs��ꂽ��S�����]�[�ǂ̎��Î��Ԃɂ��Ă̓��{���̃v���X�y�N�e�C�u�ȃR�z�[�g�����B���N�i�[��44.5���A�A�e���[�����𐫍[��10.3���B�]�[�ǂ̔��Ǘ���1�N�Ԃ�3.8���B
SPS3(Secondary�@Preventions of small Subcortical Storke)
3020��̃��N�i�[�ǂɑ���ϋɓI�Ȏ��Â̗L�p���Ɋւ��������s��������������B�R�����܂̓��^�ŏo���������ǂ��S�z����Ă������A����3.1�N�̒ǐՂœ��W���o����������0.28��/�N�Ɣ��ɏ��Ȃ������B
BAT(Bleeding with Antithorombotic Therapy)sudy
�R�����p���Ă���4009��A�ǐՊ���19�����B���W���o���̕p�x�͍R�����ܒP�ܕ��p�Q�ł�0.34��/�N�B�R�����ܕ��p�Q0.60��/�N�A���[�t�@�����Q0.62��/�N�A�R�����܁A�R�Ìōܕ��p�Q0.96%/�N
COMPASS�iClopidogrel 2 dose�@cOMarative 1-year ASessment of Safety and efficacy�j
��S�����]�[��1110��A�d�Ăȏo���i�����Ǐo���Ȃǂ��܂ށj��50�r��1.7���A75�r���p�Q��1.5���Ɨ��Q�ō��Ȃ��B�]�o����0,2��/�N
�v���^�[���i�V���X�^�]�[���j
��������cAMP����������ƌ����ÏW���}������邪�A����cAMP������z�X�z�W�G�X�e���[�[3�`��j�Q�����p�����B�o��3���Ԃōō������Z�x�ɒB���A���~��48���ԂŌ�����������B�����ɑ����p�͉t�I�ŁA���̌��ʂ͊T�˖̌����Z�x�̐��ڂƈ�v���A���^���~��48���ԂŌ��������������B���Ȃ킿�����A1���ŗL���Z�x�ɒB���邪�A���܂Ȃ���1���Ō��ʂ��Ȃ��Ȃ�B����A����~�߂Ă���A���̌��ʂ��Ȃ��Ȃ�܂ł̎��Ԃ��Z���Ƃ����̂����_�ł�����B�]�����K�C�h���C���ł́A���N�i�[�ǂ̗\�h�ɂ��R�����܂̎g�p�����߂���Ƃ��Ă��邪�A�����_�Ń��N�i�[�ǂ̍Ĕ��\�h�ɑ���G�r�f���X������̂́A���̃V���X�^�]�[���݂̂ł���B�P���Q�p����K�v������B�܌`��OD���݂̂ɕύX�ƂȂ����B
�V���X�^�]�[���̗L�����A���S���̓v���Z�{�ΏƎ����ŏؖ�
�\�V���X�^�]�[���ɂ��]�����Ĕ����X�N��26���L�ӂɒቺ�@ �o�����C�x���g�̃��X�N��54���L�ӂɒቺ�\
CSPS II�́A2000�N�ɕ��ꂽCSPS�̌��ʂ܂��Ď��{���ꂽ�Տ������ł���BCSPS�͓��{�l�̔]�[�NJ���1095���ΏۂɃv���Z�{��ΏƖ�Ƃ��čs��ꂽ�������d�ӌ���r�����ŁA�R������V���X�^�]�[���̔]�[�ǍĔ��\�h���ʂ��������B���̌��ʁA�V���X�^�]�[���͔]�[�ǂ̍Ĕ����v���Z�{�ɔ��41.7�����ƁA�����ɗ}���������B���{�l�̓��N�i�[�ǂ����p�x�ɔ��ǂ��邱�ƂŒm���ACSPS�ł��팱�҂̂ق�4����3�����N�i�[�ǂ̊��҂ł��������A�V���X�^�]�[���̓��N�i�[�njQ�̍Ĕ����X�N��43.4���A������L�ӂɒቺ�������B�R������̓��^�ɂ���ʂɏo�����X�N���㏸���邪�A�V���X�^�]�[���̓v���Z�{�Ƃ̔�r�ł������ɂ�������炸�]�o���𑝂₷���Ƃ��Ȃ��������߁A���S���ł��D��Ă��邱�Ƃ��������ꂽ�B
CSPS�ɂ��V���X�^�]�[���̃v���Z�{�ɑ���D�ʐ��͖��炩�ɂȂ������A���n�Տ��ł͑��̍R���������Ώ�������Ă���B�����Ŕ]�[�NJ��҂̔]�����Ĕ��\�h�ɂ�����V���X�^�]�[���ƃA�X�s�����̗L�p�����r�����Տ�����CASISP�iCilostazol versus Aspirin for Secondary Ischaemic Stroke Prevention�j�������ōs���A2008�N�ɂ��̌��ʂ����ꂽ�B
CASISP�ł͔]�[�NJ���720���ׂɊ���t���A12�`18�J���Ԏ��Â��p�������B���̌��ʁA���Q�̊ԂŔ]�����Ĕ����ɗL�Ӎ��͔F�߂��Ȃ��������A�]�o���̕p�x�̓V���X�^�]�[���Q�ŗL�ӂɒႢ���Ƃ����炩�ɂȂ����B�������ACASISP�����͏��K�͂ł���A�ώ@���Ԃ���r�I�Z�����Ƃ���A���̃f�[�^�����ŗ���̗D��ɂ��Č��_�����������Ƃ͓K�łȂ��B���̂��߁A������r����{�i�I�ȑ�K�͎��������߂��Ă����BCSPS II�͂����������Ӗ���������ڂ���Ă����B
�]�����w��̃K�C�h���C��
��S�����]�[�ǂ̍Ĕ��\�h�ɂ́A�R������̓��^�����������i�O���[�hA�j�B
���i�K�Ŕ�S�����]�[�ǂ̍Ĕ��\�h��A�ł��L���ȍR�����Ö@�i�{�M�Ŏg�p�\�Ȃ��́j�̓A�X�s����75�`150mg/���A�N���s�h�O����75mg/���i�ȏ�A�O���[�hA�j�A�V���X�^�]�[��200mg/���A�`�N���s�W��200mg/���i�ȏ�A�O���[�hB�j�ł���B
��S�����]�[�ǂ̂����A���N�i�[�ǂ̍Ĕ��\�h�ɂ��R������̎g�p�����߂���i�O���[�hB�j�B�������\���Ȍ����̃R���g���[�����s���K�v������ �������A���nj��N�i�[�ǂɑ���R�����Ö@�͐T�d�ɍs���ׂ��ł���i�O���[�hC1�j�B���nj]�[�ǂ̍ő�̊댯���q�͍������ǂł���A�������Ǘ�ɂ͓K���\���ȍ~�����Â��K�v�ł���i�O���[�hB�j�B�~�����ẤA���nj]�[�ǂ̐��̑�����}������i�O���[�hB�j�B
- HOME
- �Ǐ番����S�z�ȕa�C�A
�悭����a�C - �}���ň�҂ɍs���]�̕a�C
- �����ɂ��i���ɂ̒m���j
- ���ɂ̒m���i�����j
- ���� Q&A
- �Г��ɂ̗\�h
- ����ł���
- �����̓��ɁA�߂܂��A�����O��
- �߂܂������܂�
- �߂܂��A�ӂ��
- �߂܂� Q&A
- �葫�����т�܂�
- ����N�����a�C
- ���т�̒m��(��ÊW�Ҍ���)
- ����u�ɂ̎��Ö�
- �]�����Ƃ́H
- �]�[�ǂ̗\�h�@�Ƃ́H
- �]�[�ǂ̗\�h�Ɏg������
�i��ÊW�Ҍ����j - �]�[�ǐf�ÂɎg����p��
�i��ÊW�Ҍ����j - �]�[�ǂ̊댯���q
- ���Y��i�F�m�ǁj
- �A���c�n�C�}�[�a�̒m��
- �F�m��
-�A���c�n�C�}�[�a�𒆐S�Ƃ���- - ������d�Ɍ����܂��i�����j
- �炪�䂪�A�������
- �肪�ӂ邦�܂�
- �]�O�Ȃ̕a�C�i�Ǐ�ʁj
- ��̐����Ǝg�����i�����ʁj
- �S�z�ȕa�C�̏Ǐ�
- ���nj]�[��
- ���j���]�����
- �]�̕a�C�i���̑��j
- ���A���A�葫�̒ɂ݁A���e頏�
- ���t�����݂̂���
- �V�����
- �����߃z�[���y�[�W
- ���N�������
- �]�_�o�֘A�w����N�W
![�]�_�o�O�ȁ@��Ö@�l�R�T��@�R�{�N���j�b�N](../image/headerId.jpg)

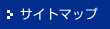
![�]�_�o�O�ȁ@��Ö@�l�R�T��@�R�{�N���j�b�N](../image/headerName01.jpg)

![�]�_�o�O�ȁ@��Ö@�l�R�T��@�R�{�N���j�b�N](../image/copy_rights02.gif)
![�]�_�o�O�ȁ@�R�{�N���j�b�N](../image/footerlogo.gif)