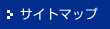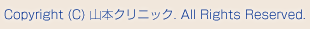小児の頭痛、めまい、頭部外傷
小児の頭痛
頭痛の大半は、検査を行っても異常の見つからない、心配のない頭痛である。しかし、なかには器質疾患(例えば脳腫瘍など)による二次性頭痛の場合があり、注意が必要である。小児の二次性頭痛は感染症による頭痛が多く、次いで頭部外傷が多い。救急外来での小児の二次性頭痛はウイルス性疾患など感染症によるもの、あるいは副鼻腔炎などによる頭痛の頻度が高く、特に2~5歳の幼児の二次性頭痛の約7割は感染症による頭痛である。髄膜炎などの危険な頭痛を見逃さないため、発熱の有無、悪心、嘔吐の有無に着目する。
「頭が痛い」と訴えていたのに、しばらくするとけろりとして遊び回っている。「もしや仮病?」、「心因性の頭痛?」のように思われがちだが、小児にも片頭痛は少なからず見られる。早い子では幼稚園に通う頃から片頭痛が起きる。成人になって片頭痛で苦しんでいる方の場合、子どもの頃に初発していることが多い。
ただし、(1)子どもと大人の片頭痛とは症状が異なるため、片頭痛と気付かれないことがある。(2)幼児、小児の場合、表現力の乏しいため訴えがはっきりしないことも多く、片頭痛と分らないことも多い。片頭痛の多くは生まれつきの体質、遺伝的要因に環境因子が加わって、片頭痛持ちになるのではないかと考えられている。両親、とくに母親が片頭痛であると、子供、特に娘も片頭痛になる確率が高いことが分っている。片頭痛の子どもには普段「車酔い」する子どもが多いという報告がある。
小児の片頭痛の特徴
- (1)頭痛が突然に起こること、また頭痛の持続時間の短い例が多い。短時間 (1時間程度)で回復する例が多く、始まりと終わりが比較的はっきりしている。国際頭痛分類第2版では、片頭痛と診断できる頭痛の持続時間は、成人が4時間以上に対し、小児では1時間以上からとされている。そこで元気だったのに急に具合悪そうになったり、また元気になったりする。
- (2)片頭痛の特徴は拍動性(ズキン、ズキン)の頭痛であることである。一方、小児の場合、非拍動性、すなわち頭全体を締め付けるような痛み方であることも多く、頭痛の拍動感を訴えない例や、はっきりしない例も多く、拍動感があるかどうかは参考にならない。
- (3)頭痛の部位は、両側性の頭痛の場合も多く、すなわち小児では両側や真ん中と表現する場合も多い。そこで片側性でなくても必ずしも片頭痛を否定する根拠にはならない。
- (4)朝に起こりやすい。寝過ぎや寝不足のときに起こりやすい。
- (5)顔面蒼白、悪心・嘔吐、腹痛などの自律神経症状を伴いやすい。
- (6)体を動かすと頭痛が強くなる、光過敏、音過敏、臭い過敏といった症状があるかどうかも参考になる。
- (7)血縁者(特に母親)の片頭痛の有無(頭痛持ちかどうか)も参考になる。
- (8)脳底型片頭痛の比率が高い。また前兆や随伴症状に「ふらつき」や「めまい」、「めまい感」を伴う例が多いことをあげる研究者もいる。
小児の片頭痛治療薬
小児頭痛の急性期第1選択薬(頓服)はイププロフェン(ブルフェン)と、アセトアミノフェン(カロナール)である。通常、アセトアミノフェンがよく使われる。いずれの薬剤も、頭痛が始まったらできるだけ早く、十分な量を使用することが勧められる。これらの鎮痛剤に、制吐剤を併用する事で、頭痛を抑制する効果はより高くなる。
カロナール(アセトアミノフェン)
本剤の添付文章によれば、通常、幼児及び小児にはアセトアミノフェンとして、 体重1kgあたり1回10~15mgを経口投与し、投与間隔は 4~6時間以上とする。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日総量として60mg/kgを限度とする。ただし、成人の用量を超えない。また、空腹時の投与は 避けさせることが望ましい。適応 小児科領域における解熱・鎮痛。
ブルフェン(イププロフェン)
イブプロフェン(5mg/kg、 5 歳以上、成人量 200mg/回で 600mg/日まで) 本剤の添付文章によれば、イブプロフェンとして、小児は、5~7歳 1日量 200~300mg、 8~10歳 1日量 300~400mg、 11~15歳 1日量 400~600mg を3回に分けて経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。保険適用は「小児での急性上気道炎に関連する解熱・鎮痛薬」。
トリプタン系薬剤
片頭痛の特効薬であるトリプタン系薬剤のうち、海外の小児に於いて、プラセボ対照群を置いた検討で有効性が報告されているのは、スマトリプタン点鼻薬(イミグラン点鼻液)とリザトリプタン(マクサルト)、ゾルミトリプタン(ゾーミッグ)の3つである。日本頭痛学会の「慢性頭痛の診療ガイドライン」では、小児のトリプタン製剤について「体重40kg以上、12歳以上の小児であれば、成人と同量のトリプタン製剤を使用可能と考える」、イミグラン(スマトリプタン)点鼻薬、ゾーミッグ(ソルミトリプタン)点鼻薬(本邦未発売)が有効かつ安全な薬剤であり、錠剤ではマクサルト(リザトリプタン)が有効かつ安全であるとの見解を述べている。しかし現時点ではすべてのトリプタン製剤の添付文書に「小児等での安全性は確立していない」と記載されている。使用するなら、スマトリプタン点鼻薬(推奨は12歳以上)と、リザトリプタン内服(20~39Kgで5mg、40Kg以上で10mg)を用いる(ただし、小児に対して両剤とも保険適用外)。
制吐薬
小児の場合には鎮痛薬の投与に先立って、制吐薬投与すべきである。その理由は小児の片頭痛発作は胃腸症状を伴っていることが多く、制吐薬の併用によりしばしば頭痛の改善が得られるからである。
ドンペリドン(ナウゼリンなど)
ナウゼリン錠5mg /ナウゼリン錠10mg、なお5mg/5mgの懸濁液がある。12歳以下では5~10mgの用量で用いる。
メトクロプラミド(プリンペラン)
プリンペラン錠5mg、なお5mg/5mlの懸濁液がある。12歳以下では2.5~5mgの投与量である。
片頭痛予防薬による治療
頭痛の程度が強く、回数が多い場合、すなわち頭痛薬の使用が月6~10日を超える場合に考慮する。また、片頭痛発作時に毎回嘔吐を伴うなど、回数が少なくても生活の支障度が高い場合も必要となる。予防薬には即効性はなく、8~12週間使用してみてはじめて効果が出始め、十分な効果がでるまでには数か月を要することが多い点を理解しておく。
小児にはペリアクチン(シプロヘプタジン)、トリプタノール(アミトリプチリン)を用いる。バルプロ酸は片頭痛予防効果で保険適用があるが16歳以下の小児での検討はなく、小児での使用は限定される。片頭痛の予防薬では、抗てんかん薬のトピナ(トピラマート)が有効で、十分許容される薬剤であるが、わが国では保険適用はない。ジヒデルゴットを使用する場合もあったが、最近、本薬剤は発売中止となった。
ペリアクチン(シプロヘプタジン)
抗セロトニン作用のため頭痛抑止効果が期待できる。就寝前2~4 mg 1回投与が安全で簡単である。増量可能であるが、多くの場合、4~8 mg/日以上に増量すると、眠気を訴える、(就寝前1回投与0.1mg/kg/日、最大4mg/日)。ペリアクチン0.2~0.4mg/Kg/日で19人のうち17人に著明改善、4人は頭痛が消失したとの報告がある。副作用には鎮静作用、体重増加、傾眠傾向がある。
ペリアクチン錠4M
1錠中シプロヘプタジン塩酸塩水和物4mg(無水物として)を含有する。
ペリアクチン散1%
1g中シプロヘプタジン塩酸塩水和物10mg(無水物として)を含有する。
トリプタノール(アミトリプチリン)
片頭痛の予防に広く使用されている薬剤である。5~10 mg を就寝前から開始し、徐々にl mg/kg/日に増量する.(0.25mg/kg/日、最大10 mg/日、就寝前分1とする。
小児周期性症候群
国際頭痛分類第2版では、小児に特有な片頭痛として「 1.3 小児周期性症候群(片頭痛に移行することが多いもの)」が加えられている。頭痛がなくとも、周期的に吐いたり、腹痛やめまいを起こす場合も片頭痛の仲間に入れられている。
小児周期性症候群
1.3.1 周期性嘔吐症
1.3.2 腹部片頭痛
1.3.3 小児良性発作性めまい
周期性嘔吐症
小児期に起こる激しい悪心と嘔吐を繰り返す発作で、発作時に顔面蒼白と嗜眠傾向を伴うことがある。発作間欠期には、症状は完全に消失する。本症候群の臨床像は、片頭痛に関連して認められる臨床像に類似する。また、これまでの研究から、周期性嘔吐症候群は片頭痛に関連した疾患であることが示唆されている。
腹部片頭痛
日常的な活動を妨げるほどの重度の痛みで、腹痛とともに食欲不振、悪心、嘔吐、顔面蒼白などを伴う。腹痛は正常な日常的活動を妨げるほど重度の痛みであるが、小児では食欲不振と悪心の区別ができないことがある。腹部片頭痛を有する大部分の小児は、後年になって片頭痛を発症することが多い。
小児良性発作性めまい
前ぶれなく生じる回転めまい発作で、数分から数時間で自然に治る。めまいと同時に片側性の拍動性頭痛を伴うことがある。
小児のめまい
子供に最も多いめまいに、起立性調節障害(Orthostatic Dysregulation: OD)によるものがある。これは「身体」の発育に比べ、循環器系や自律神経系などの発育が未熟で、追付かないことが多いことによる。急に立ち上がった時に、脳に必要な血液供給が間に合わない際に起こり、いわゆる脳貧血状態が起こる。 症状としては、立ち上がった時の「眼前暗黒感」、「ぐらぐらするめまい、立ちくらみ」、「嘔気」などである。なお回転性めまいを訴える場合、他のめまい疾患を考えるべきである。
人は起立すると、血圧が低下する。これを防ぐために自律神経系の一つである交感神経が興奮し血管を収縮させて血圧を維持し、また、副交感神経活動が低下し、心臓の拍動が増加して心拍出量を上げ、血圧を維持するように働く。起立性調節障害ではこれらの代償機構がうまく働かず、そのせいで血圧は低下し、脳の活動に必要な血行が維持されなくなる。そのため、「立ちくらみ」や「ふらつき感」が起こってくるのである。比較的身長の高い子供に発症しやすい傾向があり。特に学童期の発症が多い。また血圧が低下しやすい午前中に発症しやすく、季節としては、気温の上昇による血圧低下が起こりやすい春から夏にかけて起こることが多い。
1974年に小児自律神経研究会が作成したODの診断項目は、次のように大症状と小症状の二つに大別されている。
大症状:
A 立ちくらみ、あるいはめまいを起こしやすい
B 立っていると気持ちが悪くなる、ひどくなると倒れる
C 入浴時あるいは、嫌なことを見聞きすると気持ちが悪くなる
D 少し動くと動悸あるいは息切れがする
E 朝なかなか起きられず、午前中調子が悪い
小症状
a 顔色が青白い
b 食欲不振
c 臍疝痛(強い腹痛)を時々訴える
d 倦怠あるいは疲れやすい
e 頭痛をしばしば訴える
f 乗物に酔いやすい
g その他
起立性血圧調節障害によるめまい症状が強く、かつ頻発する場合には、塩酸ミドドリン(メトリジン、1回2mgを1日2回)がよく使われる。その他、塩酸エチレフリン(エホチール)、メチル硫酸アメジニウム(リズミック、10mgを朝1回もしくは朝夕の2回)、メシル酸ジヒドロエルゴタミン(ジヒデルゴット、2016年1月製造中止)などの薬剤が使用される。
小児の頭部外傷
小児は頭部を打撲することが成人より多い
成人と比べ小児は頭部の大きさ、すなわち頭部の体幹に対する比率が大きい。そのため重心が上の方にあることから、バランスが悪く転びやすい。また転ぶと頭を打ちやすい。さらに頭部の重量が体幹よりも重いため、転倒する際には頭部への加速度が増加し、強く打ちやすい。さらに身長が低いため目の位置が低くなり、相対的に視野が狭くなっていること、興味の対象に関心が集中してしまって全体を見たり、とっさの状況判断力や危険を予知する能力が乏しいこと、運動能力を身につける発達段階にあることから、結果として危険からの回避動作が遅れがちになることなどがあげられる。
頭を打った時には、どの程度の衝撃があったかどうかを知る必要がある。どのような状況で頭を打ったか、打った時にすぐに泣いたかどうか、それとも暫くボーッとして意識がない時期があったかどうかが大切である。打ったあとすぐに泣いて、外見上も普段と変わりがない場合、通常、泣かない程度の打撲であって、心配ないと考えて良いと思われる。
頭を打った後、経過をみる場合の注意点については、「頭を打った」、「子供さんの場合の注意点」の項を参照。
大泉門の状態で頭の中の圧を知ることができる
頭蓋骨はいくつかの骨が癒合(くっついて)して出来上がる。乳児では頭のてっぺん(頭頂部)に、骨がくっつく前の骨がない菱形の部分(穴)がある。これが大泉門で、1歳半頃までに骨癒合により閉鎖するが、この大泉門の部分は皮膚だけなので、そこを触ることによって頭の中の圧を知ることができる。正常では横になった時や泣いたり、力んだ時に圧が高くなって、少し膨らんでいる。一方、起きて座ったりしている時には、少しへこんでいるのが普通である。頭部外傷で頭の中に出血などの異常が起こると、頭の中の圧が高くなる。この場合は抱っこして起こしてみても、大泉門が膨らんだままで、押すと固く感じる。
吐いたら危ない?
子供の嘔吐中枢は敏感なので、頭を打った後に吐くことは良くある。一方、成人の場合、頭部打撲後に嘔吐がみられた場合、頭蓋内に出血している場合が多い。子供の場合、たとえ吐いても、その後、けろっとして、全身状態が良好なら一度くらい吐いても心配ないことが多い。
たんこぶができたから安心。できなかったから危ない?
たんこぶは「皮下血腫」あるいは帽状腱膜下血腫と言い、打撲で頭皮下の血管が切れてそこに血液がたまってできるものである。たんこぶ(皮下血腫)が大きい場合は強い打撲だったと考えられる。この「たんこぶは」軽く冷やしておくのが良い。すなわち、タンコブは打撲の衝撃が強ければできやすいし、弱ければできにくい。したがってタンコブが出来たから安心とは言えない。「触るとその部分がへっこんでいる」ように感じられ、陥没骨折と間違われることがある。
帽状腱膜下出血は、通常、時間が経つと吸収されるため、あわてて注射器で血液を抜くのではなく(感染を起こす危険性を避ける)、しばらく様子を見るのが良い。しかし、新生児では時になかなか吸収されず、骨のように石灰化することがある。乳児でも時間を待っても吸収されない場合、穿刺して血を抜くことがある。
脳震盪 (のうしんとう)とは?
頭部に強い衝撃を受けると脳震盪が起こる。打撲前後を正確に記憶しているかどうかを確認し、記憶があいまいだったり、打撲後しばらくの間、ボーッとして同じことを何度も繰り返し尋ねたりする場合は、脳震盪が起こっている可能性がある。脳震盪は強い打撲であった事を意味している。
脳震盪はその字のとおり、脳が急激に揺れ動かされ、一時的に脳の機能が低下した状態を言う。症状としては、一時的に意識が無くなる、記憶が無くなる、めまい感、バランス感覚がおかしくなる、頭痛、吐気、視界がぼやけるなどの症状が現れる。あとで頭を打ったことを全く覚えていないということもよくある。いずれも脳震盪だけであれば、時間の経過とともに軽快する。
頭の骨の骨折
骨折には線上骨折(ヒビが入る)と、陥没骨折とがある。骨折すると言うことは、それだけ強い外力を受けたということである。もし線上骨折がみられ、それが骨の内側にある血管溝を横切っている場合、後に頭の中に出血が起こる可能性が高いので、注意深く経過を観察する。なお小児は、一般に頭蓋骨が薄く、弾力性があるので割れて線上骨折を起こしにくいが、陥没骨折を起こすことがある。陥没骨折とは骨が「ぺコッ」とへこんだ状態になることである。陥没骨折を起こした場合、2歳頃までは骨が柔らかいので自然に治ることが多く、多少のへこみは特に問題ない。しかし骨のへこみが強い場合、あるいは脳に刺さったようになっていたりする場合、また、「けいれん」が起こるような場合は、手術で整復する場合もある。
慢性硬膜下血腫
慢性硬膜下血腫とは、頭部外傷後の慢性期(通常1~2ヶ月後)に頭部の頭蓋骨の下にある脳を覆っている硬膜と脳との隙間に血(血腫)が貯まる病気で、血腫が脳を圧迫して様々な症状がみられる。慢性硬膜下血腫は、一般に高齢者に多いが、頭部外傷後の乳児にも起こることがある。
頚椎の損傷が起こることがある
年少児の頚部筋群は弱く、一方、頭部の重量は相対的に重い。小児の頭蓋頚椎部の安定性は骨よりも靭帯に依存している。そこで頭蓋頚椎移行部でのズレ(環軸椎脱臼など)を生じやすい。このため重症外傷や受傷機転が不明な場合には、頭蓋頚椎移行部の評価を含めたほうが良い。
参考資料
- 知っておきたい学童、生徒の頭痛の知識、筑波学園病院小児科、東京クリニック小児、春期外来 藤田光江著 養護教諭用冊子
- 日本頭痛学会 慢性頭痛の診療ガイドライン2013、Ⅵ、小児の頭痛
- 子供の頭痛:日本小児神経学会
- 小児の頭痛 AD ロスナー、Pウインナー著 翻訳 寺本 純 診断と治療社
- 小児の頭痛―診かた・考え方の実践―(小児科診療 Vol.76 No.8、 2013)
- 日本小児心身医学会、起立性血圧調節障害(OD)ガイドライン
- HOME
- 症状から分かる心配な病気、
よくある病気 - 急いで医者に行く脳の病気
- 頭が痛い(頭痛の知識)
- 頭痛の知識(続き)
- 片頭痛 Q&A
- 片頭痛の予防
- 頭を打った
- 小児の頭痛、めまい、頭部外傷
- めまいがします
- めまい、ふらつき
- めまい Q&A
- 手足がしびれます
- しびれを起こす病気
- しびれの知識(医療関係者向け)
- 難治性疼痛の治療薬
- 脳卒中とは?
- 脳梗塞の予防法とは?
- 脳梗塞の予防に使われる薬剤
(医療関係者向け) - 脳梗塞診療に使われる用語
(医療関係者向け) - 脳梗塞の危険因子
- 物忘れ(認知症)
- アルツハイマー病の知識
- 認知症
-アルツハイマー病を中心として- - 物が二重に見えます(複視)
- 顔がゆがんだ、けいれんする
- 手がふるえます
- 脳外科の病気(症状別)
- 薬の説明と使い方(疾患別)
- 心配な病気の症状
- 無症候性脳梗塞
- 未破裂脳動脈瘤
- 脳の病気(その他)
- 腰、肩、手足の痛み、骨粗鬆症
- 血液検査のみかた
- 新着情報
- お勧めホームページ
- 健康一口メモ
- 脳神経関連学会リンク集